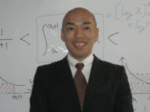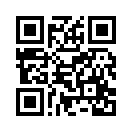数学の勉強法をメールマガジンで紹介しています。
「数学の勉強は頑張っているけど、なぜか成績があがらない」「どうやって勉強をしたらいいか分からない」
そういった人に高校数学をわかりやすく説明しています。
読者さんの声を紹介します。
--------------------------------------------------------------------------------------------
大変役立たせてもらっています。
大昔、塾に通ってた事がありますが、トントン拍子に答えを出して行くだけで、いまいち過程が分からずつまらなかったのを覚えています。
ですから、なぜこうなるか一つ一つ意味を考えることの出来る先生の数学は解いていて分かった時は格別に楽しいです。
-------------------------------------------------------------------------------------------
学校の授業では理屈を教えてくれませんが、どしてこういうことをするのか理由をいちいち説明してくれているからわかりやすいです。問題が解けてもなぜ、何のためにするのか分からないことが多々あります。その理屈を知ることができて数学が楽しくなりました。
-------------------------------------------------------------------------------------------
2010年02月13日
物理はまずは力学と電気分野を勉強しよう
こんにちは、最近はなんだか天気が悪いですね。
外をみると雪がちらついていました。
それでは、今日の勉強法です。今日は、物理の話をします。
物理は力学、電気、波動、熱力学、原子の5つの分野に分かれています。もちろんすべての分野を勉強する必要があるのですが、物理の苦手な人はまず力学と電気分野の勉強をしましょう。
国公立大学、私立大学ともに物理の受験問題は大問が3題というところが多く、たまに5題という大学があります。
もいろん大学によって、また年度によって変わってきますが、受験問題が3題のところのそのうち2題が力学、電気分野から、5題のところは3題が力学、電気分野から出題されるということが多いです。あるいはもっと力学、電気分野からの出題の割合が高い大学もあります。
大学受験は、全体で6割くらいとれると合格できるという大学が多いので、極端な話しですが、物理は力学と電気分野さえしっかりと理解できていたら大学に合格することができるのです。
物理が苦手だという高校生は本当に多いです。物理すべてを勉強しようとすると、やるべき事柄が多く嫌になってしまう可能性が高いです。
ですから、最初はよくばらずに電気、あるいは力学分野の勉強をまずはするようにしたらいいと思います。
高校数学の勉強法
外をみると雪がちらついていました。
それでは、今日の勉強法です。今日は、物理の話をします。
物理は力学、電気、波動、熱力学、原子の5つの分野に分かれています。もちろんすべての分野を勉強する必要があるのですが、物理の苦手な人はまず力学と電気分野の勉強をしましょう。
国公立大学、私立大学ともに物理の受験問題は大問が3題というところが多く、たまに5題という大学があります。
もいろん大学によって、また年度によって変わってきますが、受験問題が3題のところのそのうち2題が力学、電気分野から、5題のところは3題が力学、電気分野から出題されるということが多いです。あるいはもっと力学、電気分野からの出題の割合が高い大学もあります。
大学受験は、全体で6割くらいとれると合格できるという大学が多いので、極端な話しですが、物理は力学と電気分野さえしっかりと理解できていたら大学に合格することができるのです。
物理が苦手だという高校生は本当に多いです。物理すべてを勉強しようとすると、やるべき事柄が多く嫌になってしまう可能性が高いです。
ですから、最初はよくばらずに電気、あるいは力学分野の勉強をまずはするようにしたらいいと思います。
高校数学の勉強法
2010年02月08日
物理のセンター試験対策
こんにちは、今日は物理のセンター試験対策の話をします。
物理なんですが、5年ほど前に教科書改訂が行われました。それまでは物理1Bという科目名が物理1に変更になったわけですが、物理1Bから物理1になり極端に量が減りました。
以前は1Bで、コンデンサーや電流、力学の運動量などは物理1Bで勉強をしていましたが、それらは物理2で勉強をすることになっています。
物理1Bにはなくて、物理1になって勉強するようになったところもありますが、ごくごく一部です。
全体的に見て、あくまで私の感覚ですが、量が40パーセントくらい減ったように感じます。
ということは、センター試験は以前に比べて簡単になるような気がしますが、そうではありません。以前なら量が広かったのである程度の勉強で点数を取ることができました。
今は、量が少ないのである程度つっこんだ内容まで勉強をしないといけなくなりました。問題そのものを見ると、それほど大差がないという人もいますが、以前に比べ難しくなった気がします。
物理の勉強ですが、始めのうちは理解しやすい市販の問題集や学校で使っているテキストを使って勉強をしてもらえばいいと思いますが、最終的には教科書を徹底的に勉強するようにしてください。
センター試験では基本的に教科書の内容を超えるものは出題されません。教科書を徹底的に勉強をすることが何よりのセンター試験対策です。
それでは、物理の勉強がんばってください。
PS
昨日、大学の友達と「ネパール料理」を食べに行きました。店内は料理人も店員の人も全員外国人。たぶんネパール方面の人だと思います。
店内には、大きな曼荼羅が貼ってあり、なんだか外国に来たような雰囲気でした。
料理もおいしくて、久しぶりに友達ともあえて楽しかったです。
物理なんですが、5年ほど前に教科書改訂が行われました。それまでは物理1Bという科目名が物理1に変更になったわけですが、物理1Bから物理1になり極端に量が減りました。
以前は1Bで、コンデンサーや電流、力学の運動量などは物理1Bで勉強をしていましたが、それらは物理2で勉強をすることになっています。
物理1Bにはなくて、物理1になって勉強するようになったところもありますが、ごくごく一部です。
全体的に見て、あくまで私の感覚ですが、量が40パーセントくらい減ったように感じます。
ということは、センター試験は以前に比べて簡単になるような気がしますが、そうではありません。以前なら量が広かったのである程度の勉強で点数を取ることができました。
今は、量が少ないのである程度つっこんだ内容まで勉強をしないといけなくなりました。問題そのものを見ると、それほど大差がないという人もいますが、以前に比べ難しくなった気がします。
物理の勉強ですが、始めのうちは理解しやすい市販の問題集や学校で使っているテキストを使って勉強をしてもらえばいいと思いますが、最終的には教科書を徹底的に勉強するようにしてください。
センター試験では基本的に教科書の内容を超えるものは出題されません。教科書を徹底的に勉強をすることが何よりのセンター試験対策です。
それでは、物理の勉強がんばってください。
PS
昨日、大学の友達と「ネパール料理」を食べに行きました。店内は料理人も店員の人も全員外国人。たぶんネパール方面の人だと思います。
店内には、大きな曼荼羅が貼ってあり、なんだか外国に来たような雰囲気でした。
料理もおいしくて、久しぶりに友達ともあえて楽しかったです。